執筆:吉澤和子(Kazuko Yoshizawa, Sc.D.) 栄養疫学者/グローバル・ヘルス・ニュートリションスペシャリスト
日本の中小企業支援政策は、制度としてはよく整えられていると感じる場面が多い。一方で、その運用の現場に目を向けると、専門性の扱われ方について、少し立ち止まって考えたくなることがある。非専門的な判断が、結果として「専門的な助言」のように機能してしまう構造が、日常業務の中に自然に組み込まれているからだ。これは、特定の誰かの問題というよりも、制度の前提に由来する部分が大きい。
私自身がこの制度と向き合う立場にあるのは、仕事の内容や専門分野にかかわらず、日本の法律上、私の法人が「中小企業」に分類されるためである。専門性の高さや国際的な実務経験の有無に関係なく、一定の規模以下の事業者は、同じ支援の枠組みの中で扱われる。その枠組みの中に身を置くことで、制度の運用がどのように機能しているのかを、内側から見る機会を得た。
窓口対応の中には、専門家を支援する立場でありながら、無意識のうちに「判断する側」「教える側」に立ってしまう場面がある。専門性の前提が共有されないまま評価が行われると、その構図は、専門家の知を形式的な基準で測ることを正当化してしまう。 このような状況が見過ごされているとすれば、それは現場の問題というより、中小企業支援政策が内包する制度的な盲点ではないか。
本来の中小企業振興政策は、事業者それぞれが持つ強みや専門性を活かしながら、成長や社会的な価値につなげていくことを目指しているはずだ。しかし、運用の段階で評価の物差しが一つに寄ってしまうと、書類として整っているかどうかが優先され、内容そのものが見えにくくなることがある。その結果、支援は「後押し」というよりも、「制度に合わせるための調整」に近いものになってしまう。
こうした構造について、中小企業庁を含む政策の側で、どこまで意識的に検証されてきたのかは、必ずしも明らかではない。非専門性が専門性として通用してしまう運用が、本当に中小企業の多様な成長につながっているのか。その問いは、これから丁寧に共有されていく必要があるように思う。
国際的な研究・プロジェクトの現場では、専門家が専門家として役割を果たせるよう、判断の範囲や責任の所在があらかじめ整理されている。そうした経験を踏まえると、日本の中小企業支援においても、「誰が、どの専門性をもって、何を判断しているのか」を整理する視点があってもよいのではないかと感じる。
制度に合わせて書類を書き直すこと自体は、実務として珍しいことではない。ただ、その過程で、どの専門性がどのように評価されているのかを問い直すことは、決して無駄ではない。中小企業振興政策が、事業者一人ひとりの知や経験を活かす仕組みであり続けるために、制度の運用について、少し立ち止まって考える余地はまだ残されているように思う。
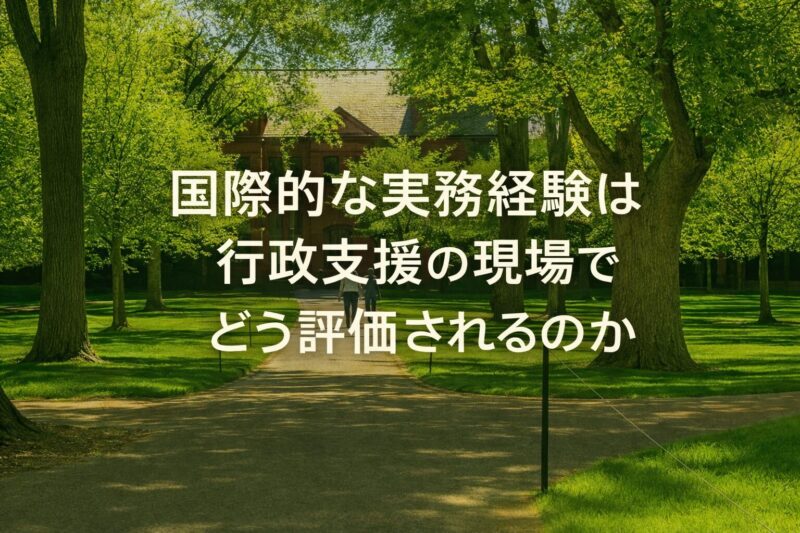


コメント