専門性がそのまま評価されるとは限らない──行政支援や補助金申請の現場に立ったとき、私はその事実を改めて実感した。博士号を持ち、国際機関でのプロジェクト運営や、ハーバード大学での国際共同研究倫理審査の経験を積んできたとしても、日本の制度の中では、その前提が共有されていない場面が少なくない。しかし同時に、制度の内側には、専門職を支えうる手厚さと可能性も確かに存在している。
起業と社会実装──キャリアの延長線上にある新たな挑戦
私は、自分のキャリアで経験したものを社会実装するために起業した。博士号の資格を活かし、私は国連機関やWHO(世界保健機関)の派遣国で保健・栄養プロジェクトに携わり、東ティモールでは日本の国際協力による約2億円規模のプロジェクトを策定した。そこでは、貧困や栄養、SDGsに関わるKPIを意識しながら、実行可能性を極めて現実的に組み立てることが求められた。限られた資源をどう配分し、成果をどう測定し、誰のために透明性を確保するか――それが「開発」と「ガバナンス」を結ぶ実務の核心である。
公金の扱いと研究ガバナンス──公立大学とハーバード大学で学んだこと
公立大学における厳格な研究費運用の経験は、公金を扱う責任と制度の複雑さを実感する、実地のガバナンス教育だった。さらに、ハーバード大学では、日本で開始した研究を国際共同研究へと発展させるため、IRB(倫理審査委員会) の承認を取得した。研究倫理教育プログラムである CITI(Collaborative Institutional Training Initiative:共同機関教育プログラム) の認定を受け、医学、法律などを含む異なる専門分野と倫理観をもつ複数のPh.D.ホルダーによって構成される IRB とのやり取りを通じて得た研究倫理の実践的経験は、国際標準のコンプライアンスを身につける貴重な機会となった。
行政支援の現場で感じた「制度の文法」
日本では中小企業支援に力を入れており、伴走支援や書類整備の仕組みが整ってきた。中小企業庁を中心とする制度の厚みに私は深く支えられている。一方で、補助金申請の現場では、国際的な視座よりも「地域」「雇用」「波及効果」といった評価軸が前面に出る。ここには、行政文書ならではの制度的な文法が存在し、専門職の成果を「伝わる言葉」に翻訳することが欠かせない。
専門職・評価・言語化──見えない前提が浮かび上がる瞬間
社会に埋め込まれた無意識の前提や慣習は、説明や対話の場で言語化しようとする時に浮かび上がる。専門的な表現の削ぎ落としを求められる一方で、専門性の核心は言葉の選び方に宿る。特に女性研究者・起業家の立場では、その評価過程に見えない前提が作用しやすい。だからこそ、制度に合わせて「書き直す」だけでなく、制度が専門職の知を理解できるように、言葉を編み直す必要がある。
「先に公開する」ことの意味──時系列エビデンスとしてのブログ
本稿を、申請や行政対応に先んじて公開するのは、意図的な選択である。それは、起業、プロジェクト設計、行政支援の活用といった一連の実践を、研究で培った倫理的視点とともに、社会に可視化しておくことに意味があるからだ。このような発信は、外部証拠としての時系列エビデンスとなり、公開日時というタイムスタンプを通じて、実践の過程を客観的に記録する。これは、説明責任(accountability)と透明性(transparency)を満たし、専門職としての信頼性を補強する行為でもある。
結語──社会実装の文法を更新する
私は、制度に合わせて書類を「書き直す」だけでなく、現場で人が動くような言葉で社会を変える書き換えをめざしている。今回の記事も、行政支援の仕組みを実際に活用しながら得た経験を記録し、共有する試みのひとつだ。ガバナンスと倫理に根ざした実務知を社会に還元することで、専門職の知が現場とつながる。小さな一歩だが、このような発信が次の実践を生み、制度の側の仕組み(=社会の文法)も少しずつ更新されていくと信じている。
執筆:吉澤和子(Kazuko Yoshizawa, Sc.D.) 栄養疫学者/グローバル・ヘルス・ニュートリションスペシャリスト
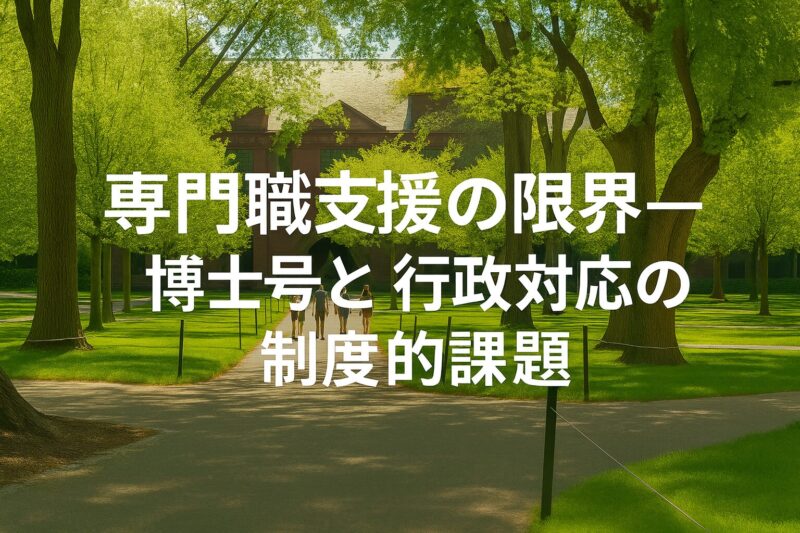

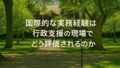
コメント